

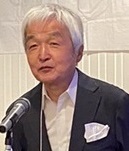
帰島の12日、離島の16日に子どもたちがそれどれ墓参りをするとのことで、家室では車のない盆となった。
12日墓参りが終わり、仏壇の内敷、提灯を飾り、精霊様の準備をする。周りの整理が終わると、窓際に座りいつもの飲みを始める。本はテーブルにあった五木寛之の「大河の一滴」、いつも途中で投げ出すため、拾い読みでページを捲る。
13日は8時から棚経が始まるため、それまでに家までの道、空地の草刈りを行う。お寺さんが通る道並みは何とか刈取る。棚経が終わると観音堂への100段の階段を上り、墓参り、その足で母の実家へ挨拶に向かう。佐連へは片道1km余りであるが、この暑さ、橋のアップダウンが少々躰に堪える。帰宅ご昼食を摂り窓際の椅子に・・・
五木寛之の本を読んでいて、以前プレジデントでの彼の投稿記事を思い出す。本棚を捜すと2019年「孤独を100倍楽しむ方法」、2022年の「捨てない生き方」があり取り出す。前稿は『論語』の「和して同ぜず」、『荘子』の「君子の交わりは淡きこと水のごとし」を引いて話を進める。後稿は「依り代」(よりしろ)をキーにモノが記憶を呼び起こすとを説く。昔から一人でいることが苦にならない性であり、頷きながら読み進んだ。
14日は盆踊り会場の設営。6時30分開始(家室時間6時)「ああでもない」「こうでもない」「誰か指示しろ」等声が聞こえるのは毎年のことで2時間程度で終了する。
夜は20時から盆踊り。今年は例年と様子が変っていた。「家室音頭」が聞こえると一番に踊りを始めるが今年は続いてきそうな人が見当たらない。少し間を置き同級生と踊り始める。2~3周程度踊ると輪になった。今年は我々の年代の孫に当たる小学校低学年以下」の子が多かったように思う。小学生以下の年代には花火のセットを配布30個程度が無くなったと聞いた。
15日は家の周りの残りの草刈り。擁壁の草や、気になる木等を切り取り9時過ぎまで汗をかく。 この盆は同級生のお母さんの初盆であり仏壇に線香でもと思っていたが、帰島客で人も多いと思い、夜のお寺で行われる万灯会で供養させてもらうことにした。帰路、盆会場に寄り挨拶のみで帰路についた。
16日朝、気が付けば5時30分過ぎ、急ぎ精霊様を下げ流灌頂の会場に、舟を降ろす場には間に合った。流灌頂を見送った後、墓に参り盆の終わりを告げる。何組かの人と言葉を交わし今年の盆は終わった。
家室も暑い夏でした。救われたのは夜の涼しさ、盆前の雨のお蔭でしょうか・・・よく汗をかき、よく酒を飲み、その分よくお茶も飲み、疲れのみが残った盆であった。
10時40分頃、子どもが墓参りに帰り、その後離島する。